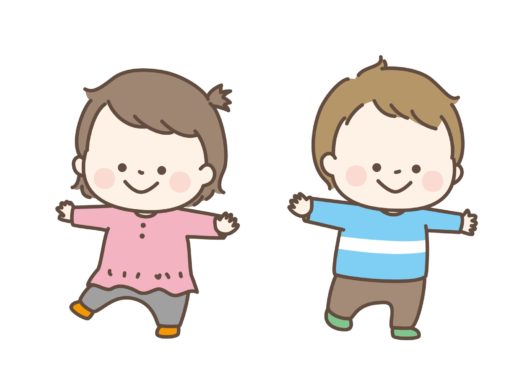この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは、2歳になったばかりの男の子を育児中のもこです。
息子はことばが遅くて、1歳半健診で引っかかっていたため、2歳になるすこし前に発達相談に行ってきました。
この記事では、2歳児健診の内容をまとめます。
Contents
1歳半健診で要観察になりました
1歳半健診では、以下の理由で引っかかり、要観察になっていました。
1歳半健診で引っかかった理由
- 単語をほぼ喋ることができない
- 応答の指さしができない(例:「ワンワンどれ?」に対する指さし)
くわしくは以下の記事にまとめています。
自治体によって進め方は異なるでしょうが、問診や内容はどこも同じような感じではないでしょうか。
2歳児健診は何をするの?発達相談の内容

2歳児健診とは
1歳半健診で要観察になった場合など、希望すれば2歳児健診を受けられます。
定期の1歳半健診や3歳児健診とちがって、2歳児健診は任意で行われるものです。
自治体によっては積極的に行なっていないところもあるようです。
わたしの市では、1歳半健診のあとに希望を確認され、2歳頃に発達相談員さんによる発達相談がありました💡
2歳児健診の内容
発達相談の内容は、以下です。
発達相談の内容
- 言葉や行動に関する問診
- 応答の指さしができるかチェック
- 型はめができるかチェック
- おもちゃであそんでいる様子を観察
息子は応答の指さしはいまだにできません。
型はめはすぐにできました。
ことばは以下のことは喋りますが、名詞は言えません。
- 1〜5まで順にかぞえる
- ABCDまで順に唱える
- いや
- 痛い
- あーん
- あちっ(熱い)
- いないないばあ
- ババ・パパ(意味はわかっていない)
「ママ」や「マンマ」すら言えないのに、数字や英字を喋るようになったことにはびっくりしたし、発達相談員さんも優しいから褒めてくださりました。
数字は読めるから、それだけは言葉と結びついているようです。
あとはたまに親をまねして、単語の頭文字だけなら言うことがあります。
(例:にんじん→ 「に!」など)
だからそのうち名詞を喋りだすことを期待したいのですが、応答の指さしができないこと、ほかにも自閉症の特徴に当てはまることが多くて心配です。
ことば以外にも、普段の様子を確認されたため、ありのままの成長を答えました。
- 車が大好きで、プラレールにハマっている
- 褒めてほしくて拍手を求めてくる
- 要求は増えたが、指さしではなく「クレーン現象」で親の手を引き目的地まで連れて行く
- 親が人が指さしたものを見ない
- 指先は器用(スプーンで上手に食べられる、細かいものを積み上げる)
- ごっこあそびができるようになった(しまじろうのぬいぐるみにお世話する)
- よく笑う
- 親以外の人に関心が薄い
- 好きなものに熱中する
話の流れでいろいろ質問されましたが、特に以下についてはしっかり確認されました。
確認されたポイント
- 親の言うことを理解しているか
- 名前を呼んだら振り返るか
- どんなあそびが好きか・集中してあそぶか
息子は親の言うことはまあまあ理解している(「くっく履いて」「ちょうだい」「おいで」などに答える)のですが、それはジェスチャーがあるからわかっている気もするし、指示が通らないことも多いです。
名前を呼んだら振り返ります。
健診でイスに座っているとき以外は、大人しくおもちゃであそんでいました。
クレーン現象や、指差ししないことについてはなにも言及されませんでした。
2歳児健診に行かない人もいる?自費の自治体もある
2歳児健診は任意であり、強制ではありません。
「1歳半健診で引っかかったけど、特に心配していないから行かない」
「2歳頃に急激に言葉を喋りだすようになった」
などの理由で行かない方もいるようです。
自費の自治体もあるようですから、わざわざお金を出して行きたくない、と思う方もいるかもしれません。
ただ1歳半健診で保健師さんから提案されて、その後も親が発達についてすこしでも心配なことがあるなら行ったほうがいいと思います。
今後の対応や支援を考えてくれるなど、子どもにとっていい機会を与えてもらえるかもしれません。
2歳になっても喋れないと発達障害・自閉症?

子どもが2歳になっても喋れないと、不安になってしまいますよね。
わたしも不安です。
これからどういう成長をたどるのか、先がわからなくて怖いです。
この時期は個人差が大きいとはいえ、2語文(「マンマちょうだい」など)を喋り出す子も多いと聞くし、やはり「うちの子は遅いんだな」と感じる機会が多いです。
ただ、市で行われる健診や発達相談では「発達障害の診断」がされることはありません。
診断は専門の医師にしかできないし、3歳になるまでは正確にはわからないといわれています。
そもそも明らかな遅れや特徴がなければ、医師にすら診断がむずかしいといわれるくらい、軽度の場合は定型発達と線引きのむずかしいものだそうです。
わたしも今回の健診では、「発達障害」のワードが出ることはなく、
「成長を見守りましょう」
「また不安なことがあれば相談してください」
というお話で、終わりました。
2歳児健診では、いまの成長を見守る【経過観察】か、「発達障害の疑い」として【療育などの支援】を勧められるケースが多いようですよ。
言葉の教室に応募しました
ネットやSNSで調べていると、対応が早い自治体では、1歳半健診のあとすぐに療育につなげるケースもあるようですから、わたしも今回療育を勧められるものだと思っていたし、早いほうがいいと聞くため期待もしていました。
しかし、わたしの市ではそこまで早い対応はとっていないのか、けっきょく経過観察となりました。
 もこ
もこ
そしてまた、数ヶ月後に保健師さんによる発達相談を行い、そこで市が実施する「ことばの教室」を利用するか検討するそうです。
しかし、「希望者が多く抽選になるため、必ず利用できるとは限らない」とも言われました。
1回の定員は15名程度らしく、それで抽選になるなんて、意外とことばの遅れに悩んでいる親御さんが多いのかもしれません。
どうしても利用したいと思い、いまの時点で「利用希望」ということを伝えました。
また療育についても確認したのですが、あまり積極的に勧めることはしていないのか、いまは必要ないと捉えられたのか、「成長をみながら、次回相談しましょう」というお返事で終わってしまいました。
ことばの教室は、市で開催される親子教室・交流の場です。
発達に遅れがある子どもと交流できる機会は、わたし的には支援センターにあそびに行くより気負いしなくて楽しそうと思っています。
こどもちゃれんじプチでごっこあそびができるようになった

ことばが遅い息子が『ごっこあそび』ができるようになりました。しまじろうのおかげで。
親のまねをするのって自閉傾向の子どもにはすごくハードルが高いこと。
子どもの発達段階でみられるあそびのひとつ。
子どもが関心をもった「何か」になったつもりで、その対象の「ふり」や言葉の「まね」をするあそび方のこと。
1〜2歳くらいでみられるようになる。
いつものように息子に夜の歯磨きをしようとわたしがスタンバイしたとき、急にしまじろうのぬいぐるみに歯磨きしてあげるふりをして、ニヤニヤこっちにドヤ顔して仰天しました。
 もこ
もこ
ごっこあそびは1歳でできる子もいますが、息子はバイバイなど簡単なまねすらあまりしない子どもだから、本当にこのときはびっくりうれしかった。
ほかには『車の型はめパズル』も気に入っていて、マッチングの力が養われました。
春のキャンペーンがやっていたので入会したのですが、届く教材ほとんどに興味津々で真剣にあそんでいるのでよかったです。
これまで、ほかのおもちゃがあれば必要ないし、増えたら邪魔になるだけ、とか思っていましたが、実際届いたらやっぱり古くからつづく教材なだけあって、本当に子どもの発達にいいものを研究されているんだろうな、と感動しました。笑
こどもちゃれんじ